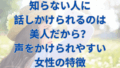絵を描いていて「肌の色がうまく出せない」と感じたことはありませんか?特にうすだいだい色は、思っているよりも奥が深く、いざ混色しようとすると濁ったり暗くなったりしがちですよね。
この色はただの「オレンジがかったベージュ」ではなく、微妙なバランスで表情が変わる繊細な色でもあります。肌色に近いトーンとしても使えるだけに、失敗したときのがっかり感は大きいかもしれません。
この記事では、うすだいだい色を絵の具・色鉛筆・クレヨンなどさまざまな道具でどう作るか、そして表現に活かすための工夫まで詳しく紹介します。自分の作品にぴったりの色を見つけたい方にぴったりの内容です。
「もうちょっとこの色が出せたら」と感じた経験があるなら、きっと参考になりますよ。色作りに自信を持ちたい方は、ぜひ読み進めてください。
うすだいだい色とは?特徴と使い方

うすだいだい色は、「肌色」や「ペールオレンジ」とも呼ばれることがあり、特に人物画やイラストで使われる定番の色です。
でも、実はこの色、単なる明るいオレンジではないのをご存じですか?どんな色なのかを正しく知ることで、表現の幅がぐっと広がります。
うすだいだい色の基本と肌色との違い
「うすだいだい色」と「肌色」は似ているようで少し違います。うすだいだい色は、日本の伝統色の一つで、橙色に白を加えたような明るくやわらかな色合いです。
肌色はその人の肌のトーンによって変化しますが、うすだいだい色はもう少し画一的な色として使われる傾向があります。
また、うすだいだい色は感情を表現するうえでとても便利な色です。温かさややわらかさ、安心感などを視覚的に伝えることができるため、キャラクターの肌や背景、小物にも多用されます。
似たような色でも微妙なニュアンスを意識して使い分けることで、絵の印象がグッと変わりますよ。
うすだいだい色の使いどころと英語表現
イラストでは主に肌のベースカラーや頬の赤みに重ねるような表現に使われます。ファッションアイテムや雑貨の色としても人気があり、柔らかく自然な雰囲気を演出したいときに活躍します。
水彩やアクリルなど、どんな画材でも相性がよく、初心者からプロまで幅広く愛されている色といえるでしょう。
英語では「Light Orange」や「Pale Orange」と表記されることが多く、色味の説明には「peach(ピーチ)」や「flesh tone(フレッシュトーン)」なども使われます。
海外の色名表記を参考にすれば、グローバルな視点での色使いもスムーズになります。
うすだいだい色を絵の具・色鉛筆・クレヨンで作る方法
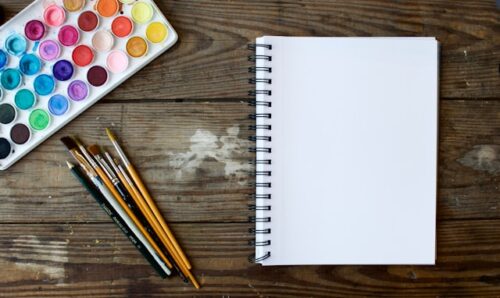
うすだいだい色を思い通りに再現するには、使う画材によって少しずつ手順やテクニックが変わります。
ここでは、絵の具・色鉛筆・クレヨンの3つの道具での作り方を紹介します。どれも身近に手に入る素材なので、すぐに試せるのも嬉しいポイントです。
絵の具で作る手順と道具選び
まずは、絵の具でうすだいだい色を作る方法です。基本となるのは、赤・黄・白の3色です。このうち、赤と黄をオレンジ寄りになるように混ぜてから、白を少しずつ加えていくと、明るくやわらかいうすだいだい色に近づきます。
具体的な配合の目安は以下の通りです。
- 赤:1
- 黄:1〜1.5
- 白:少しずつ調整
水彩なら水の量でも調整できますが、濃くしすぎると彩度が上がりすぎることがあるので注意が必要です。アクリルやポスターカラーを使う場合も、まず少量ずつ混ぜて様子を見るのがコツです。
道具としては、パレット、筆、きれいな水、ティッシュなどを用意すると安心です。
色鉛筆・クレヨンの混色テクニック
色鉛筆やクレヨンでは、絵の具のように混ぜることはできませんが、重ね塗りによって近い色を作ることができます。おすすめの基本色は、オレンジ系、ベージュ系、そして白系です。
たとえば、薄いオレンジを塗ったあとに白でぼかすように重ねたり、肌色のベースに少しだけ赤みを足して温かみを出したりと、重ね方次第でニュアンスが大きく変わります。
芯が硬めの色鉛筆なら細かい調整がしやすく、柔らかいクレヨンなら全体的にふんわりした仕上がりになります。
あまり力を入れすぎず、何度かに分けて塗り重ねていくのが自然に仕上げるポイントです。いきなり本番に描く前に、紙の端で試してみるのがおすすめですよ。
重ね塗りや描写のポイント
肌に近い色を表現するには、ただ1色で塗るのではなく、陰影や質感を意識した重ね塗りが効果的です。特に頬や鼻のまわりなど、ほんのり赤みを帯びた部分は、うすだいだい色に赤やピンクをうっすらと加えることでリアルな表現になります。
逆に影になる部分には、グレーやブラウン系を薄く重ねることで立体感を演出できます。画材によっては色の定着が弱いこともあるので、最後に定着スプレーなどを使うと安心です。
どの道具でも、色を重ねるときは「少しずつ」が基本です。調整をしながら、理想の色に近づけていくプロセスもまた、創作の楽しさのひとつかもしれません。
理想の肌色を作るためのコツと応用

肌の色は人によって異なり、うすだいだい色をベースにしても、そのままでは「なんだか合わない」と感じることがあります。そこで役立つのが、彩度や色味を調整するテクニックです。
ここでは、理想の肌色に近づけるためのコツを紹介します。
彩度や色味を調整するテクニック
色を明るくしたいときは白を加え、落ち着かせたいときはグレーや少量の青を混ぜる方法が有効です。これによって、鮮やかすぎるオレンジ系の肌色が、より自然なトーンに変化します。
また、肌に赤みを加えたいときはローズ系、黄みを加えたいときはオーカー系の色を少しだけ重ねると効果的です。ただし、やりすぎると違和感のある色になってしまうこともあるので、変化を確認しながら少しずつ加えるのがポイントです。
慣れてきたら、少し青や緑を足して影のニュアンスをつけるのも面白い表現になります。影色までこだわると、イラストに一段深みが出ますよ。
ペールオレンジやバリエーションの作例
うすだいだい色の中でも「ペールオレンジ」と呼ばれるトーンは、特にアニメ風イラストや児童向けの作品でよく使われています。これは赤みが少なく、より明るく柔らかい印象を与える色です。
作例としては、以下のようなバリエーションが考えられます。
- 通常のうすだいだい色:赤+黄+白で標準的な肌色に
- ペールオレンジ系:黄を多めにし、白で明度を高く
- 日焼け風:オレンジに少しブラウンを混ぜて濃く調整
こういった微調整ができるようになると、人物の雰囲気や年齢感まで表現に取り入れることができます。
アート作品での肌色の表現方法
うすだいだい色は人物表現に欠かせない色ですが、リアルさを出すには工夫が必要です。
たとえば、光の当たり方を意識して、明るい部分には白や薄い黄色を加え、影の部分にはグレーや青みのある色を加えると、奥行きが出てきます。
また、肌色は単体で完成させるよりも、背景や服の色とのバランスをとることで、自然な印象になります。全体の色味を確認しながら、必要に応じて調整していくと良いでしょう。
肌の色は、単なる「ぬる」作業ではなく、全体の雰囲気をつくる大事な要素です。じっくりと観察しながら、色のバランスを取っていく楽しさを味わってみてください。
うすだいだい色を活かしたセットや作品づくり

うすだいだい色は、単色で使うのはもちろん、他の色と組み合わせることで一層魅力的に見せることができます。ここでは、配色のヒントや作品への応用アイデアを紹介します。
セット構成のアイデアと配色例
うすだいだい色は、暖かみがありながら主張が強すぎないため、他の色と合わせやすいのが特徴です。以下のようなセット構成がおすすめです。
- うすだいだい × ミントグリーン:やわらかく爽やかな印象に
- うすだいだい × モカブラウン:落ち着いた大人っぽさを演出
- うすだいだい × サーモンピンク:かわいらしさや親しみやすさをプラス
これらは、イラストの背景、小物、衣服の色などに取り入れることで、全体に統一感を持たせながら印象的な表現を作ることができます。
セットで色を考えると、どんなシーンで使うかもイメージしやすくなります。たとえば「朝の光」「カフェの空間」「優しい会話」など、テーマをもとに配色を考えてみるのも楽しいですよ。
作品におけるうすだいだい色の活用例
うすだいだい色は、人の肌を表す以外にも、いろいろな用途に使えます。たとえば、絵本の動物の毛並み、パンやスイーツなどの食べ物、布や壁の質感など、あたたかく穏やかな雰囲気を出したい場面で活躍します。
実際に、優しいタッチのイラストや、ナチュラル系のデザインではこの色がよく登場します。色数を抑えつつ表現したいときにも便利で、主張しすぎず自然になじむ点が魅力です。
また、他の暖色系とのなじみもよいため、イラストのアクセントとして部分的に使うのもおすすめです。影の縁にほんのり加えることで、柔らかな印象を保ちながら深みを出すことができます。
まとめ
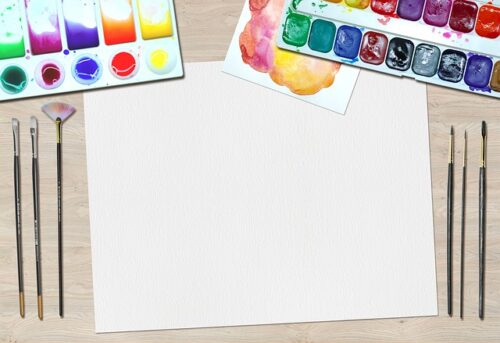
うすだいだい色は、一見シンプルに見えて、実はとても表現力豊かな色です。絵の具・色鉛筆・クレヨンなど、道具ごとに作り方や重ね方の工夫があり、自分の好みに合わせて自在に調整できます。
重要ポイントをもう一度整理しておきましょう。
- うすだいだい色は肌色やペールオレンジとも呼ばれるやわらかな色
- 絵の具では赤・黄・白のバランスがカギ、少しずつ調整するのがコツ
- 色鉛筆やクレヨンでは重ね塗りで近づけ、濃淡をつけると効果的
- 彩度や色味を調整することでリアルな肌色に近づけられる
- 配色を工夫することで、作品全体の印象にも大きな変化が生まれる
思った通りの肌色が出せないもどかしさを、少しずつ色を探る楽しみに変える。それが、うすだいだい色の魅力でもあります。
自分だけの色にたどり着けたとき、きっと作品づくりがもっと好きになるはずです。